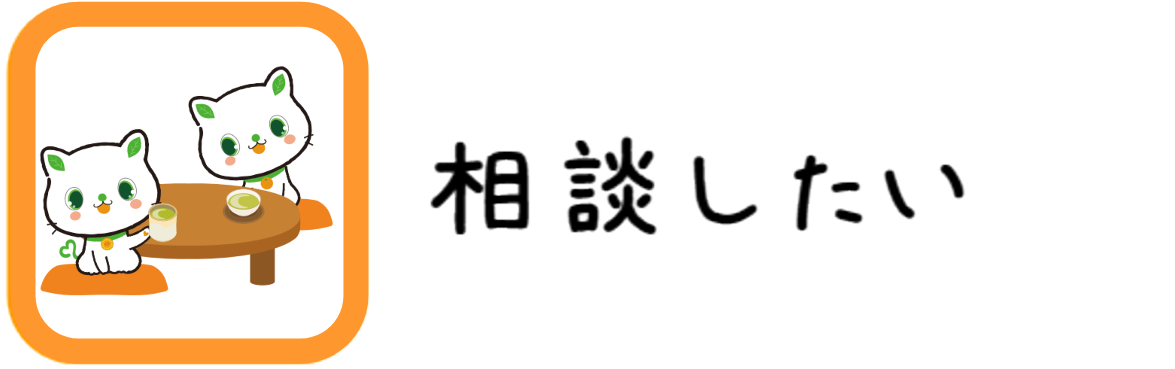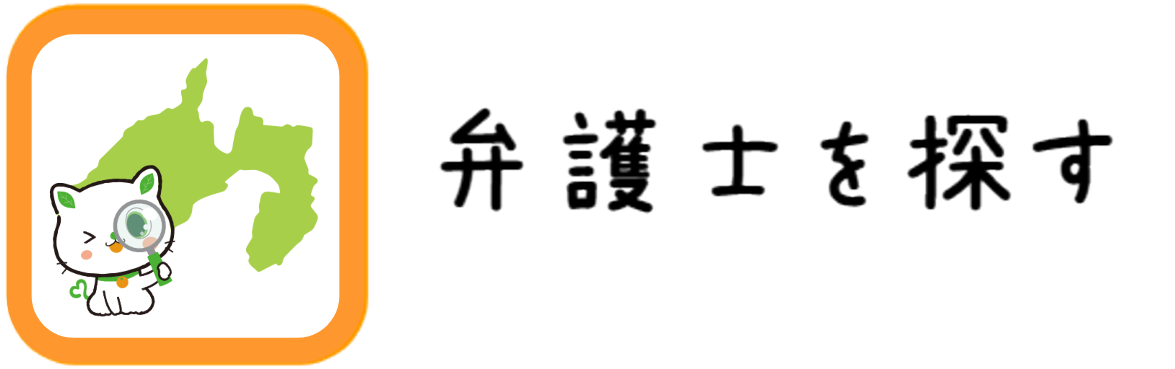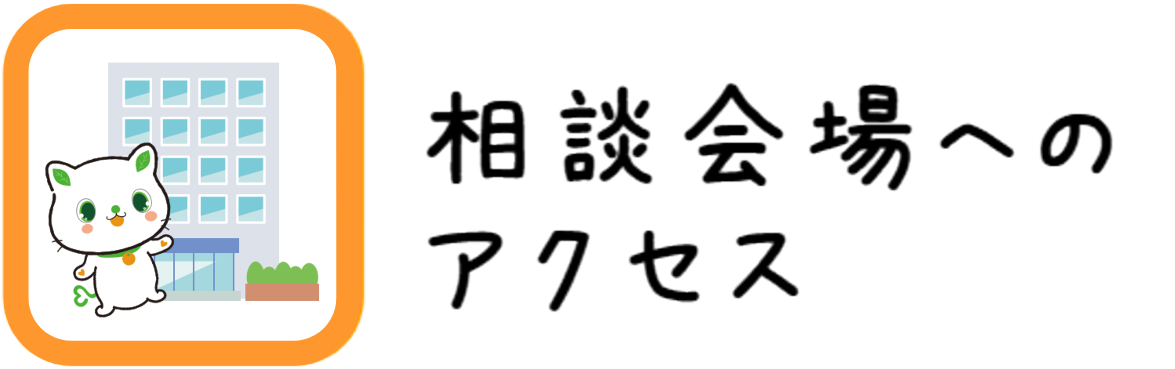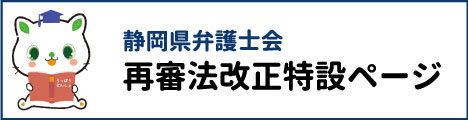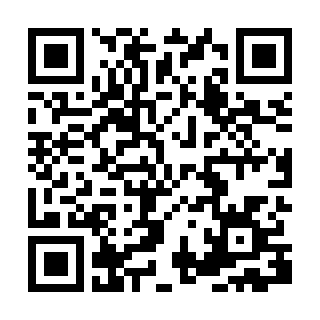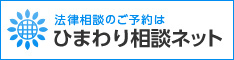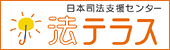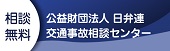2015年1月26日に召集された第189回通常国会において,「通信傍受法の拡大・要件緩和」及び「捜査・公判協力型協議・合意制度の導入」を含む刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(以下「本法律案」という。)が審議された。本法 […]
- 静岡支部
 054-252-0008
054-252-0008 - 浜松支部
 053-455-3009
053-455-3009 - 沼津支部
 055-931-1848
055-931-1848
会長声明・総会決議等 2015年
【声明・決議・意見】 「通信傍受法の拡大・要件緩和」及び「捜査・公判協力型協議・合意制度の導入」を含む刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に強く反対し撤回を求める声明 2015年11月27日
【声明・決議・意見】 静岡県弁護士会歴代会長有志による安全保障関連法案の廃案を求める声明 2015年8月30日
政府は,昨年7月に集団的自衛権を容認する閣議決定をすると共に,今国会に安全保障関連法案(以下「本法案」といいます。)を提出しました。その後,本法案は審議不十分のまま本年7月15日衆議院において強行採決され,現在参議院にお […]
【声明・決議・意見】 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の新設 等に反対する会長声明 2015年7月24日
政府は,2015年3月6日に出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の一部を改正する法律案(以下「本改正案」といいます。)を提出しました。 この法案は,①上陸許可や在留資格変更許可等を受ける際に,偽 […]
【声明・決議・意見】 「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」に反対する会長声明 2015年7月24日
昨年11月の衆議院解散に伴い廃案となった「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(以下「カジノ解禁推進法案」という。)が,自由民主党,維新の党及び次世代の党などの超党派の議員から構成される国際観光産業振興議員連 […]
【声明・決議・意見】 災害対策を理由とする「国家緊急権」導入の動きに反対する会長声明 2015年7月24日
与党自由民主党(以下「自民党」という)は,災害対策に必要だとして,日本国憲法に「国家緊急権」を導入する準備をしています。 国家緊急権とは,戦争・内乱・恐慌・大規模な自然災害などの非常事態において,憲法秩序を一時停止して非 […]
【声明・決議・意見】 少年法適用年齢引き下げに反対する会長声明 2015年7月24日
第1 声明の趣旨 少年法の適用年齢については,現行の20歳未満とする規定を維持するべきであって,18歳未満への引き下げには強く反対します。 第2 声明の理由 自由 […]
【声明・決議・意見】 安全保障関連法案の成立に断固反対し,廃案を求める会長声明 2015年6月23日
政府は,自衛隊法・武力攻撃事態法・PKO協力法など改正10法案を一括した「平和安全法制整備法案」と,国際紛争に対処する他国軍の後方支援を随時可能とする「国際平和支援法案」を今国会に提出し,現在国会での審議が行われています […]
【声明・決議・意見】 弁護人接見の盗聴に対し強く抗議する声明 2015年4月24日
袴田第二次再審請求事件の審理が行われている東京高等裁判所の即時抗告審の審理において,検察官から弁護人に開示された証拠の中に,静岡県警察清水警察署内での弁護人と袴田氏本人の接見を録音したテープが袴田事件弁護団に […]
【声明・決議・意見】 「労働基準法等の一部を改正する法律案」に反対する会長声明 2015年4月24日
政府は,本年4月3日,「労働基準法等の一部を改正する法律案」(以下「本法案」という)を閣議決定し,国会に提出した。 本法案は,企画型裁量労働制の対象を,従来から認められていた「事業運営に関する事項について,企画,立案,調 […]
【声明・決議・意見】 静岡市消費生活センターの「格下げ」に対する会長声明 2015年2月24日
静岡市は,本年4月から,現在は課相当である消費生活センターを,生活安心安全課の一部局(係)に格下げする機構改革を行うとのことである。 2005年に政令指定都市となった静岡市は,2007年に静岡市消費生活条例を全面改正した […]
【声明・決議・意見】 商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和に抗議する会長声明 2015年2月4日
経済産業省及び農林水産省は,本年1月23日,商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令(以下「本省令」という。)を定めた。 当会は,2014年4月21日付け「現行の商品先物取引法下における不招請勧誘禁止規制の緩和に反対す […]
【声明・決議・意見】 TPP(環太平洋戦略経済連携協定)の締結に反対する会長声明 2015年2月3日
2013年に我が国が交渉に参加したTPP(環太平洋戦略経済連携協定)は,2014年に入り,12カ国間の関係閣僚会合がインドネシア,ベトナム,オーストラリア等において何度も開かれ,また,日米間での実務者協議も頻 […]

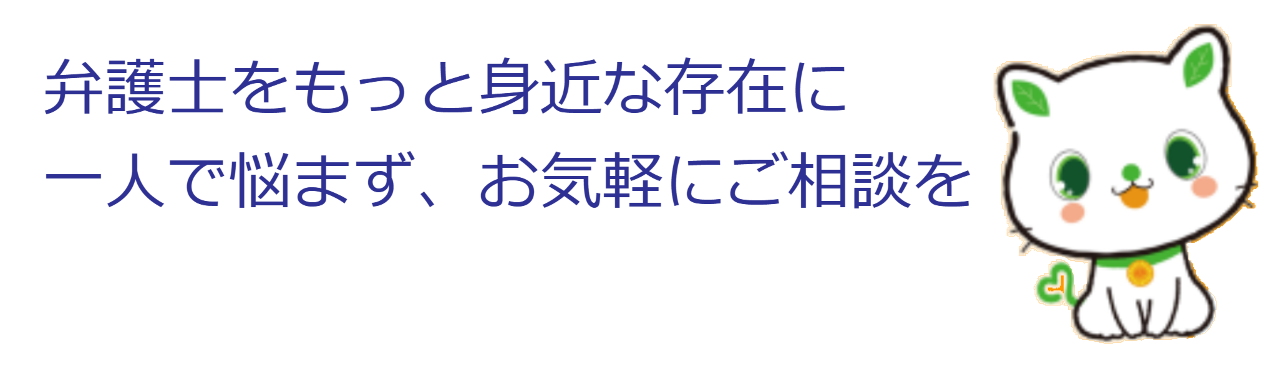
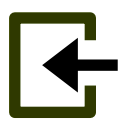 会員専用
会員専用
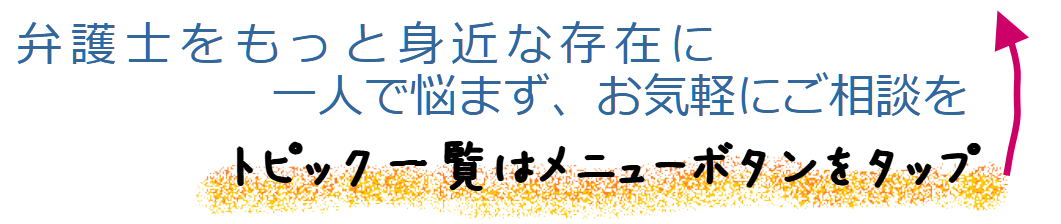

 ツイッター
ツイッター