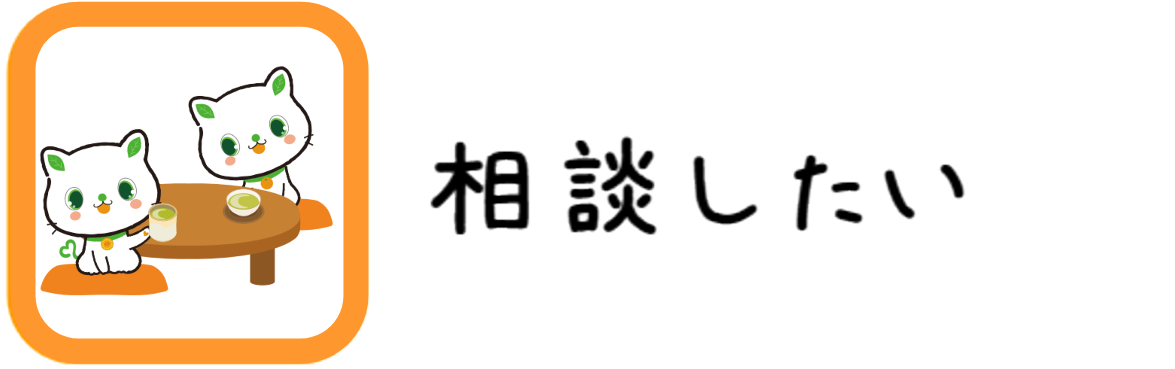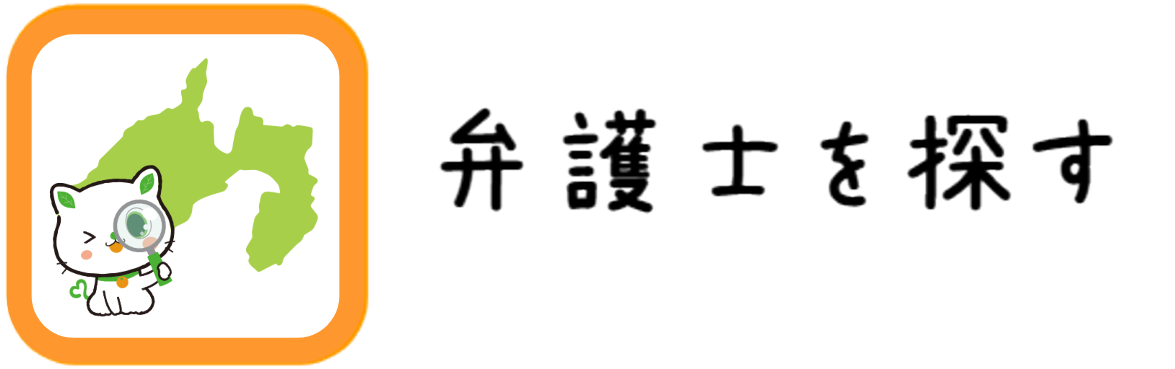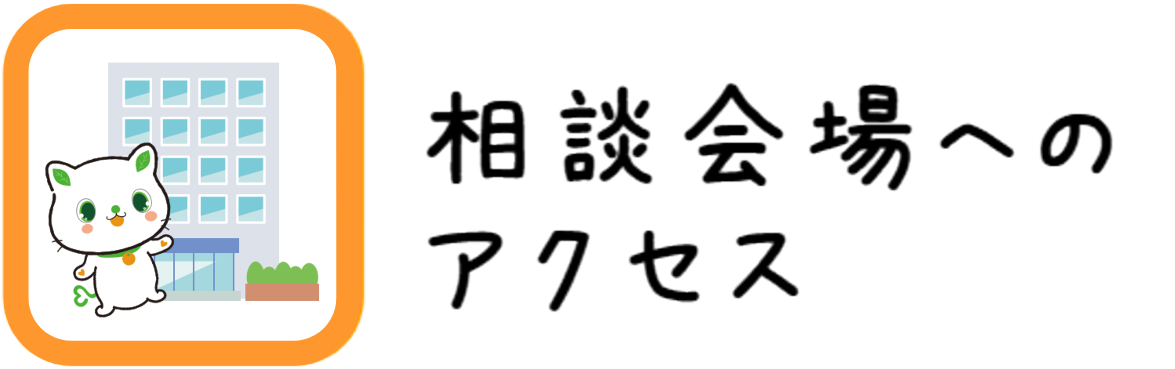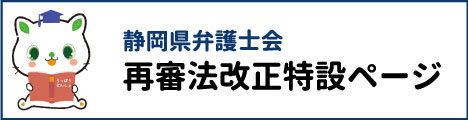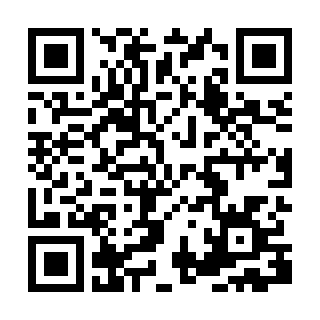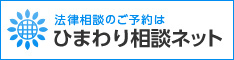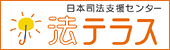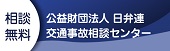11月3日は文化の日です。
文化の日は、1946年に日本国憲法が公布された日です。日本国憲法が自由と平和を重視し、自由と平和は文化にとって重要な意義を持つことから「文化の日」と名付けられたとされ、国民の祝日に関する法律では、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」日と定められています。
そこで、「自由」「平和」「文化」の観点から、現在、私たちが置かれている社会状況と憲法との関わりを考えてみたいと思います。
まず、「自由」について
昨年、静岡地方裁判所で袴田巌さんに対して再審無罪判決が言い渡されました。えん罪は、身体生命に対する個人の「自由」を奪う国家による最大の人権侵害です。袴田さんは、不当な取調べにより自白を強要され、ねつ造証拠に基づく死刑判決を覆すまでに逮捕から58年を要しました。このような被害を繰り返さないためには、取調べの可視化、そして刑事訴訟法再審規定(再審法)の改正が不可欠です。特に、えん罪被害の早期解決には、再審法改正による①再審請求審における証拠開示の制度化、②再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止などが必須です。超党派の「えん罪被害者のための再審法改正を実現する議員連盟」が衆議院に提出した「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」は、これらを適切に反映した法案です。当会は、この法案の早期成立を求めます。
次に、「平和」について
本年は、第二次大戦終結から80年目に当たります。日本国憲法は、この大戦による惨禍の反省のもとに成立し、戦争放棄と戦力不保持を定める憲法9条の「平和主義」は世界にも広く知られています。憲法9条を基にした外交交渉や人道的な国際貢献によって築かれた戦後日本の平和国家としての実績は、世界に誇るべきものです。10年前、いわゆる安保法制が成立し、以後、当会は、日本弁護士連合会や全国各地の弁護士会とともに、その違憲性を一貫して訴えています。しかし、政府は敵基地攻撃能力保有に向けた取組みや防衛費の増額を進め、憲法9条は試練に立たされているといわなければなりません。当会は、恒久平和主義、国際協調主義に基づく外交により国際平和の維持に努めることを、政府に求めます。併せて、今後も、街頭宣伝活動や映画上映会、講演会などを通じて市民の皆さんと平和について考え、行動していきます。
そして「文化」について
今、日本社会は多様な文化との付き合い方を模索しているように感じます。憲法が掲げる基本的人権の保障という理念の下、様々な文化的ルーツを持つ人々が互いに尊重しあい、それらを融合する新たな文化も形成され、より豊かな社会となっていくことを期待します。また、社会の文化的発展に寄与する学術は、日本国憲法では学問の自由として保障されています。本年、日本学術会議に関し、その独立性、自律性に大きな制限を設ける日本学術会議法案が成立しました。日本学術会議は、政治権力からの弾圧によって学術研究の自由が奪われた歴史的な経験を踏まえ、政府から独立した立場で、時の政府に対し、科学的な根拠に裏付けられた提言をする役割を担ってきました。今回の法案成立は、学術への政治的判断の介入として極めて憂慮すべき事態で、学問の自由に対する重大な脅威になり得るものです。当会は、この法案に一貫して反対し、本年5月7日および7月23日に会長声明を出しました。過去の反省を基に学問の自由が保障された歴史的経緯を踏まえ、研究者、科学者の独立性が確保され、科学の恩恵の下で平和が維持される社会を求めます。
当会は、日本国憲法公布の日である「文化の日」に当たり、改めて、日本国憲法の理念を守り、弁護士の使命である基本的人権の擁護と社会正義の実現のための活動に全力を挙げて取り組むことを表明します。
静岡県弁護士会
会長 村松 奈緒美
印刷用PDFはこちら


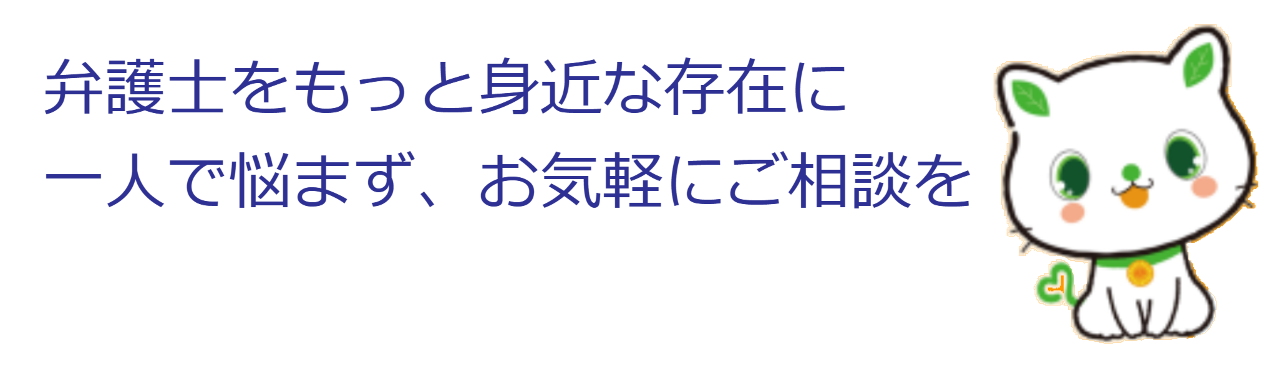
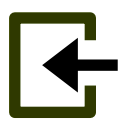 会員専用
会員専用
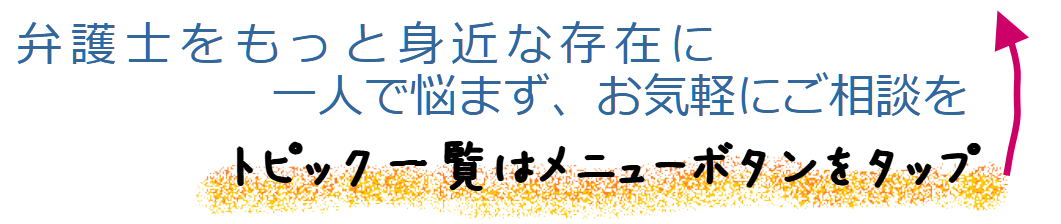

 ツイッター
ツイッター