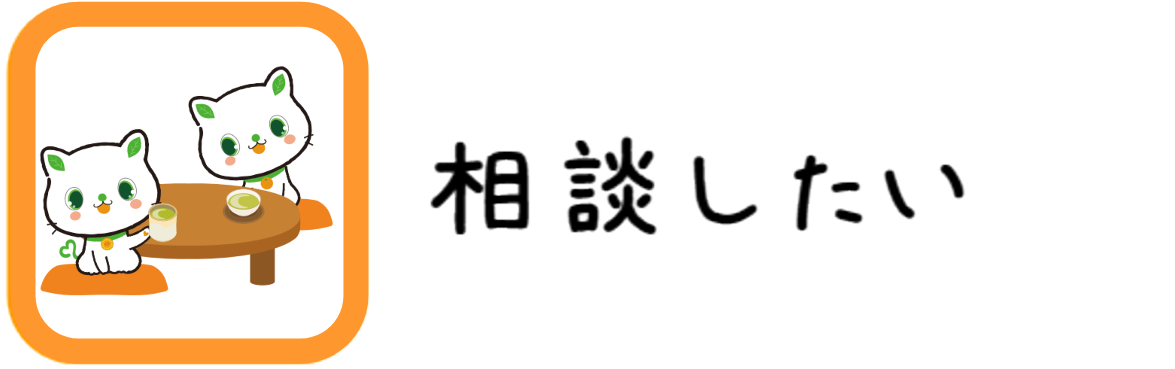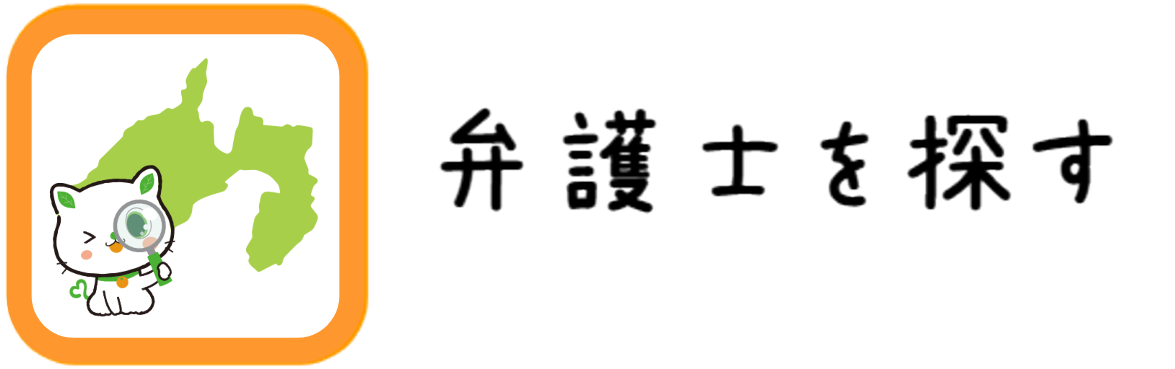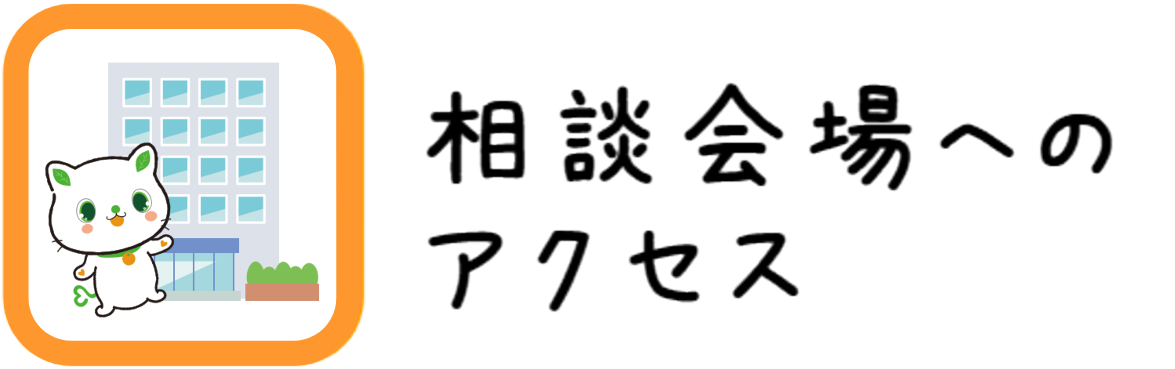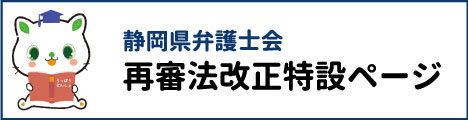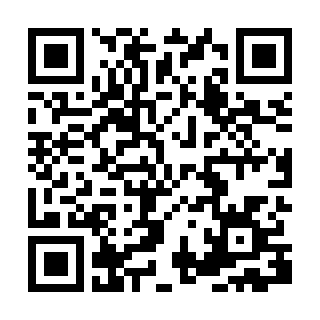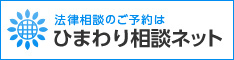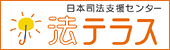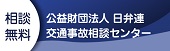- 当会は、本年5月7日付で「日本学術会議法案に反対する会長声明」を発出し、本年3月7日に政府が国会に提出した日本学術会議法案は、学問の自由(憲法23条)に由来する学術会議の独立性・自律性を大きく損なわせ、 ナショナル・アカデミーたる組織の根幹部分に大きな制限を設けるものであるとして、これに反対した。
-
しかし、本法案は、本年6月11日に国会で成立した(以下、成立した日本学術会議法を「新法」という)。
新法では、従前の日本学術会議法(以下「旧法」という。)の前文にあった「科学が文化国家の基礎であるという確信」「わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献」という理念、及び学術会議が職務を「独立して」行うという旧法3条の文言が削除され、「その運営における自主性及び自律性に常に配慮しなければならない。」(新法2条2項)との規定とは裏腹に、選定助言委員会(同26条・31条)、運営助言委員会(同27条・36条)、日本学術会議評価委員会(同42条・51条)など、政府を含む外部の介入を許容する新たな仕組みが幾重にも盛り込まれている。
また、新法により日本学術会議は法人化されるが、新法人発足時における候補者選考委員会による会員予定者の候補者の選考(同附則6条、7条)により、諸外国の多くのナショナル・アカデミーが採用している標準的な会員選考方式であるコ・オプテーション(現会員が会員候補者を推薦する方式)が採用されず、会員選考についての日本学術会議の自律性が損なわれるおそれがある。
当会は、日本学術会議法の成立に強く抗議するものである。 - 新法については、衆議院において11項目、参議院において14項目の附帯決議が採択された。この中には、「政府は、日本学術会議が我が国の科学者の内外に対する代表機関としての役割及び機能を十分に発揮することができるよう、会員の選任、科学的助言等、運営及び活動における日本学術会議の独立性、自主性及び自律性を尊重すること。」「設立時の会員の選考について、コ・オプテーションの理念に配慮すること。」など、日本学術会議の独立性と自主性の尊重と擁護及びそれを基礎づける学問の自由の保障への配慮を求める積極的な諸項目が盛り込まれており、これは国会における激しい論戦の成果である。当会は、国会の意思としてのこの附帯決議の実現を強く求めるものである。
-
また、政府は、新法について、日本学術会議の独立性と自主性を高め機能強化を図るものと繰り返し説明してきたのであるから、2026年10月の新法人発足まで、多くの問題を含んだ新法の具体的運用を、日本学術会議の独立性と自主性を堅持する観点から、日本学術会議と徹底的に議論して構築する必要がある。特に、重要なのは新法人発足時の会員選考についてである。新法附則6条は、新法人の会員予定者の候補者は候補者選考委員会が選考し(同条2項)、同委員会委員は会長が任命する(同条4項)と定めるところ、同条4項は、現会員の同委員会委員への就任を排除していない。したがって会長は、現会員による次期会員の選考というコ・オプテーション制を持続するために、候補者選考委員を現在の会員から任命することを積極的に進めることができる可能性がある。会長による候補者選考委員会委員の任命は内閣総理大臣が指名する有識者との協議が必要とされているが(同条6条5項)、政府は、その際も会長の判断を尊重する必要がある。
同附則5条によれば、新法人の会員予定者の候補者選定は、現会長が、候補者選考委員会の選考に基づき、現在の日本学術会議幹事会の議を経て、総会の承認を得るものとされており、日本学術会議の協力なしには新しい日本学術会議は成立しない。政府は、日本学術会議の自主性を尊重する具体的運用を構築することにより、日本学術会議との信頼関係を再構築するしかない。 - よって、当会は、政府に対して、国会附帯決議にある日本学術会議の独立性、自主性及び自律性の尊重という立場に立って、日本学術会議と誠実に協議を進めることを求めるものである。
2025年(令和7年)7月23日
静岡県弁護士会
会長 村松 奈緒美
静岡県弁護士会
会長 村松 奈緒美
印刷用PDFはこちら


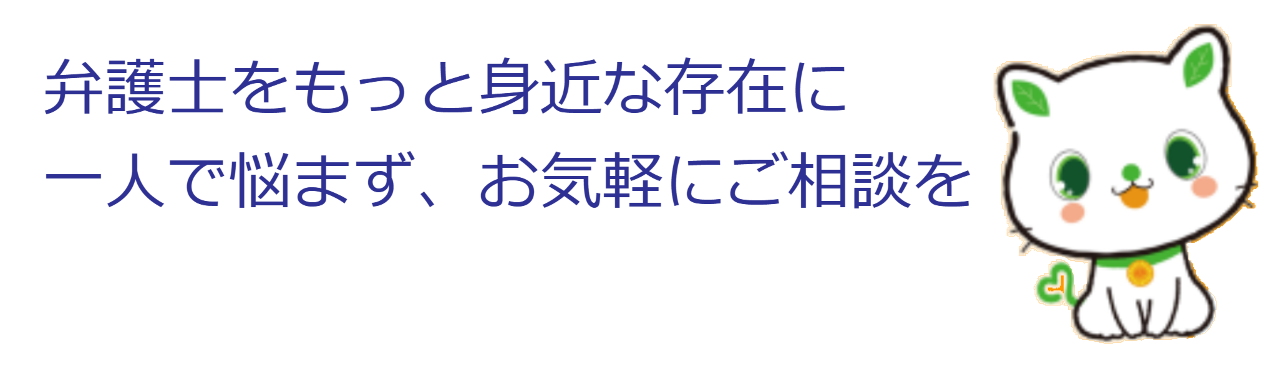
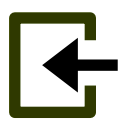 会員専用
会員専用
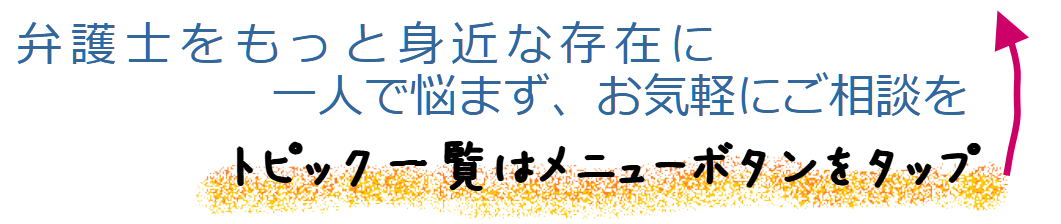

 ツイッター
ツイッター